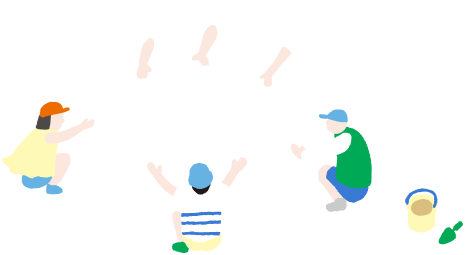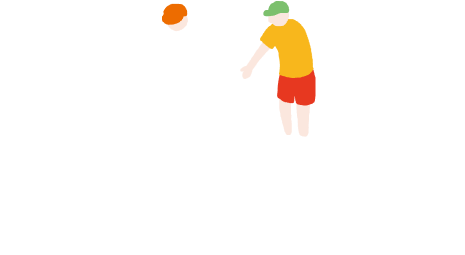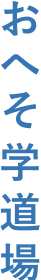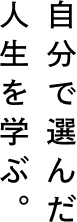SAGA Design Crossing』登壇









おへそグループ「小さな芸術家たちのアート展~冒険~」
【おへそグループ「小さな芸術家たちのアート展~冒険~」】
いつもおへそグループの取り組みにご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。
これまで3年間、佐賀大学美術館にておへそグループのアート展を開催し、子どもたちそれぞれの表現に感動の声をたくさんいただきました。
今年度からは、場所を「てつがく珈琲」に移し、より身近に楽しめる形で開催いたします。
子どもたちが自然物を使って表現した「冒険」をテーマにしたアート作品を、
てつがく珈琲の店内に展示いたします。
ご家族皆さまでお気軽にご覧ください。
展示期間:
2026年(令和8年)1月26日(月)~ 2月27日(金)
展示場所:
てつがく珈琲 店内
鑑賞について:
お店の営業時間内に、どなたでも自由にご覧いただけます。
※てつがく珈琲で、美味しいコーヒーと共にご家族でゆっくりとお過ごしください。
統括園長登壇のお知らせ「SAGA Design Crossing」
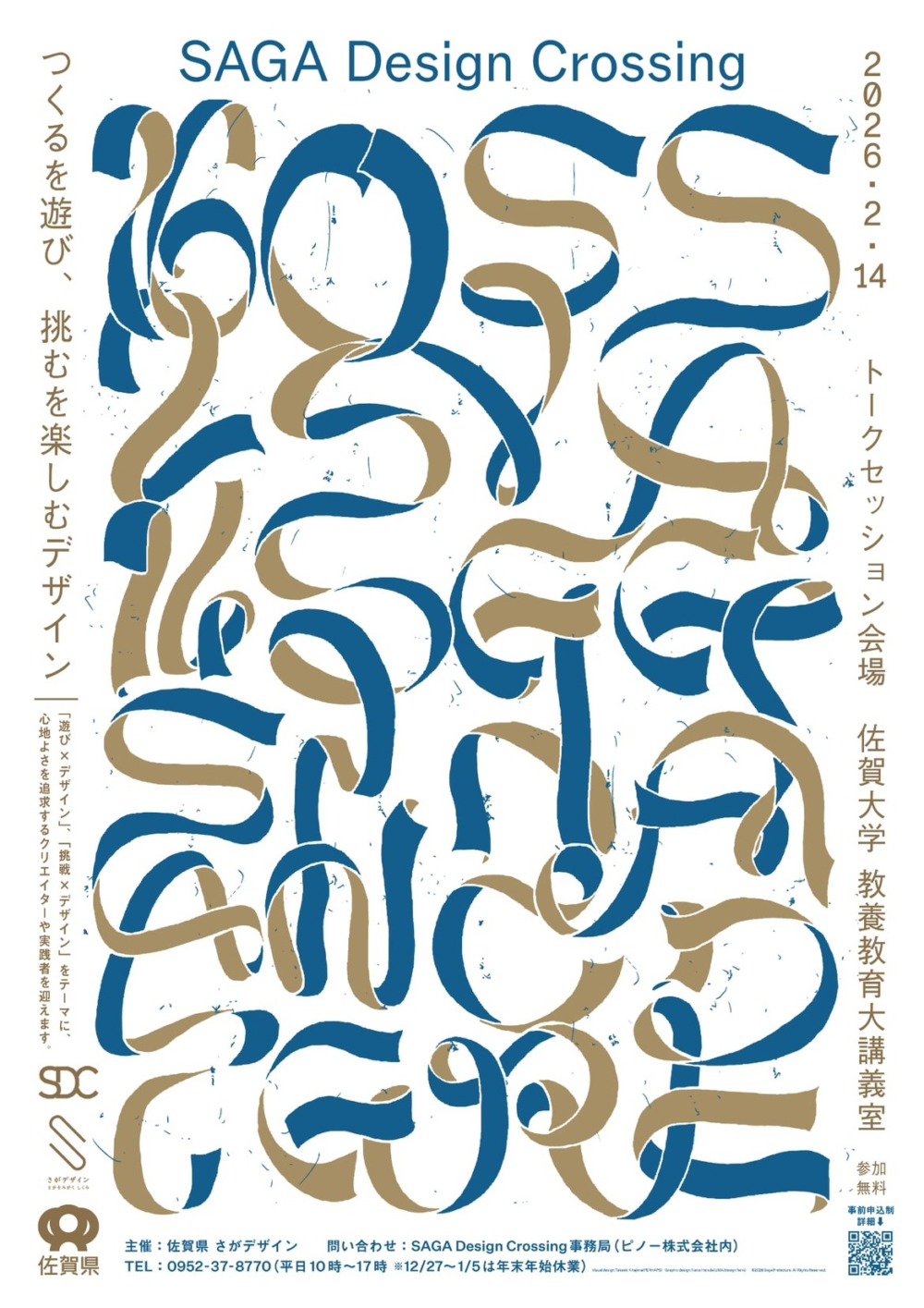
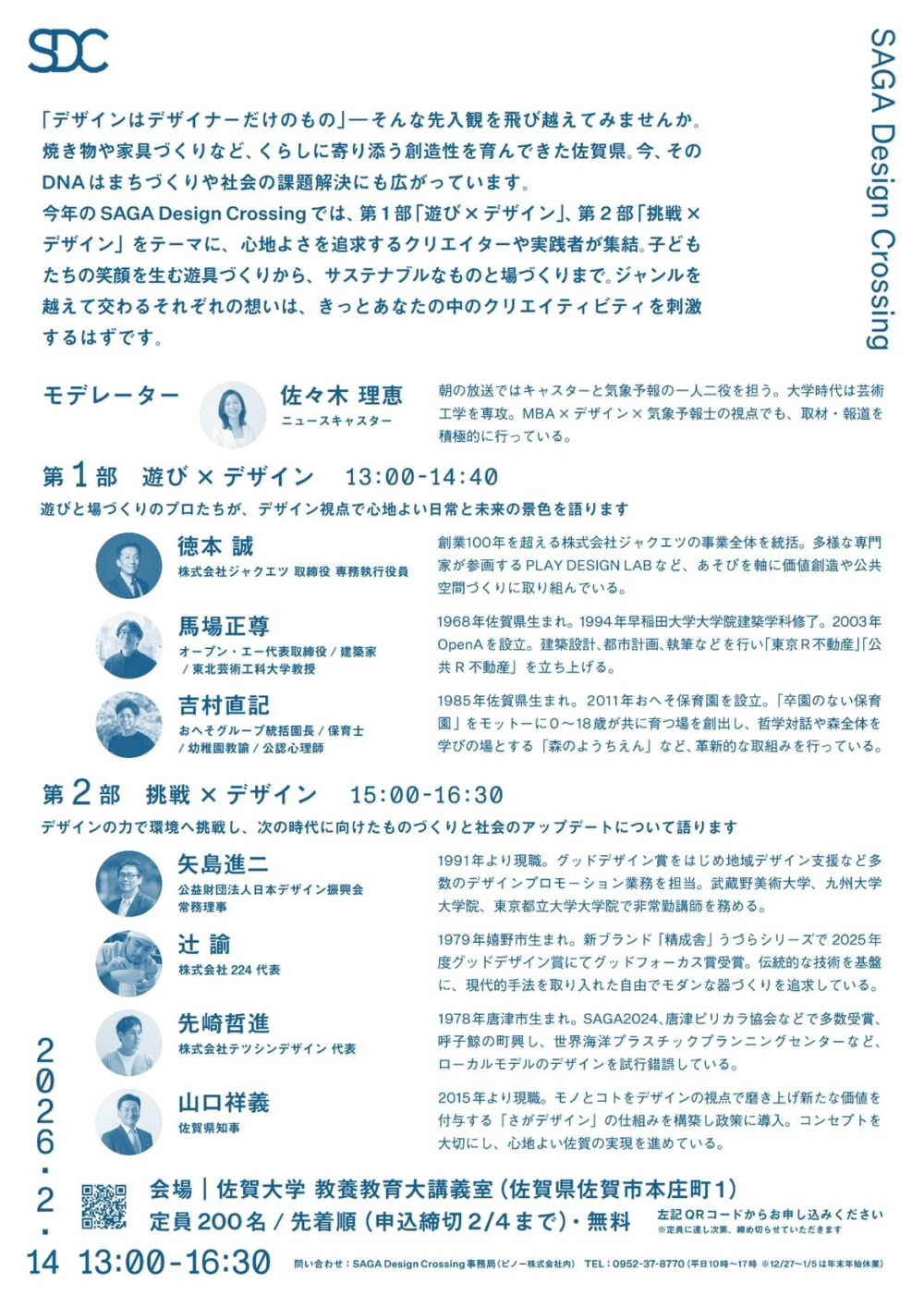
おへそグループ×フィンランドフェア in SAGA イベントのお知らせ
佐賀県佐賀市にある「おへそこども園」
森のようちえんに見る自然との関わり、家庭や園に流れる“
北欧で感じた学びをきっかけに、参加者一人ひとりが「
カフェのようにあたたかい雰囲気の中で、感じて、語って、
ミニ講話以外の時間帯は、
テントブースにてお子さまも大人も楽しめるファイヤースターター
自然物でのアート等の「森のようちえん体験」ができます。
お子さまに人気の「マシュマロ焼き体験」もあります。
皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。
―――――――――――――――――――――
■おへそグループ統括園長 吉村直記氏によるミニ講話
「〜フィンランド視察で出会った“しあわせな子育て・保育”」
12月7日(日)13:00-14:30(要事前申し込み)
・会場:ギャラリー白磁
・定員:約30名 ※先着順
・登壇者:おへそグループ統括園長 吉村直記
おへそグループ主任 本山菜月
・内容:①フィンランド視察レポート
②“しあわせな子育て・保育”を語り合うワーク
・対象:北欧の子育てや教育に興味のある方すべて
・申込みフォーム:https://forms.gle/
12月7日(日)11:00-13:00 /14:30-17:00
 森のようちえん体験コーナー
森のようちえん体験コーナー○ファイヤースターター
○自然物を使ったアート(
○マシュマロ焼き体験
○北欧の森の焚き火をイメージしたあたたかいひととき
・会場:アリタセラ北側駐車場
・参加費:500円
・対象:未就園児〜大人の方
※天候など実施日時・内容が変更・中止になる場合がございます。
(メディア出演のお知らせ)子どもたちへ熱中症講座
大塚製薬様、溝上薬局様のご協力で開催しました「熱中症講座」の様子が、
佐賀テレビさんとFBSさんに取り上げていただいております。
佐賀テレビ
https://youtu.be/Y-cVdMDOsTA?si=fYAi-KAujacazfs8
FBS
https://news.ntv.co.jp/n/fbs/category/life/fsd75d243b745b4c7db324a031f8f49786
SAGA DESIGN AWARD 2025 受賞のお知らせ
【SAGA DESIGN AWARD 2025 受賞のお知らせ】
佐賀からはじまる、佐賀を心地よくする「デザイン」を発見し、讃え、県民の皆さまへ広く知っていただくアワードです。
おへそグループは、
保育園の枠組みを超えた誰もがいていい場のデザイン「子どもとおとなと地域をつなぐインクルーシブコミュニティ」(資料はこちらから)
というプロジェクトで評価され、[入賞]となりました。
https://saga-design-award.jp/award/185/
保護者様や地域の皆様のおかげさまです。
いつもありがとうございます。